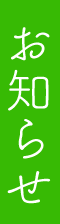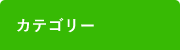みなさん、ラジオをふだん聴きますか。副院長の森豊和です。こんにちは。
ラジオを聴く理由は、好きな芸能人が出演するから、特定のパーソナリティーの話が楽しいから、災害時の情報を得るため、色々あると思います。
不登校であったり、学校になじめない、ひいては社会になじめない人たちにとっても、ラジオは大切な友人であることが多いです。TVやインターネットでもいいと思うのですが、なぜ、あえてラジオを選ぶのでしょう。
2025年4月6日川嶋あいさんの番組「明日への扉 ~いのちのラジオ+~」に、レディオキューブFM三重のアナウンサー代田和也さんが出演され、不登校だったときラジオに助けられたという話をされていました(こちらのblogにアーカイブあり 71回)。
同様の話をしたFM三重の特番は今でもYouTubeで聴取できますが、そのなかで代田さんは、「日曜の夜にすべてのFMラジオが終わっていくなか、電波の範囲が広いからAMラジオでまだ聴ける局はないか?とアンテナを伸ばして全方位を探って、やっとのことで広島からの電波をキャッチした」という内容を話されています。
ひとりぼっちのくらやみで、「だれかいないか」とよびかけて、はるか遠くから答えてくれたラジオ。その話を聞いて、私は「となりのトトロ」のようなふしぎな生き物があらわれて、隣に座ってくれるようなイメージが浮かびました。
代田さんは「ラジオは、お前がんばれよとか励ますわけでもなく、ただ、ずっとそこにあってくれた」と語っています。この「そこにある」ということは精神療法において大切なありかたです。ラジオが社会になじめない人たちに愛される理由の一つではないでしょうか。TVは基本的にTV側から情報の一方通行ですし、インターネットのSNS等は時に誹謗中傷の嵐ですから。
ユング派のカウンセリングの草分けである河合隼雄先生は、カウンセリングのあるべき姿は、何もしないことを頑張る、ただそこにあるということだといいます。本当になにもしないわけではなく、その人の可能性を信じて寄り添うということです。
甲本ヒロトさんは、盟友ミュージシャンのことをほめるときに「なんか、そこに居るんです。ワタナベマモルは」という表現をします。実際に甲本さん自身のたたずまいも、凄むわけでも影響を与えようとするわけでもなく、ただ、そこに居ます。
代田さんが学生時代のフェイバリットして挙げるBUMP OF CHICKENと同じように、THE BLUE HEARTSの歌詞は、こうすべきとリスナーに押し付けるのではなく、ただ、僕はこう思った、こういう出来事(物語)があった、と、その場に置かれるだけです。自分が正しくて大人が悪いといった分かりやすい構図のようで、実はそうではない。
最初期の曲のひとつ、「少年の詩」では、「ナイフを持って立ってた」と繰り返されますが、悪い大人をやっつける。俺は正しいとかではない。自分の中に、ひょっとしたら悪と呼ばれるような衝動があるかもしれない、ということを提示するだけ。
河合先生は、こういった社会から逸脱した子どもたちの行動、悪の衝動を適切に扱わなければいけないと語ります。それは自立とか成長とかプラスの方向の変化の始まりかもしれないからです。
不登校だって同じ。無理して学校行き続けて自殺するよりはいいですし。代田さんは不登校になって昼夜逆転がちになって聞き出した深夜ラジオで、「こんな自由な大人がいるんだ。価値観は一つじゃないんだ」というような衝撃を受けたそうです。自分を肯定してくれるような。ラジオはずっとそこにあって、双方向です。メッセージを送って読まれると1対1で尊重される。社会とつながっている感覚があります。同じ時間をリアルタイムで共有している。パーソナリティーとリスナー1人1人が対等の関係性です。
ピーター・バラカンさんの番組で記憶に残っていることがあります。おそらく50代以上の方のお手紙でしょう。
クラッシュは「ロンドン・コーリング」収録曲のようなシンプルなパンク・ロックがいいと思っていたけど、妻は3枚組「サンディニスタ!」のような多様性を好んだ。妻が死んでから独りで「サンディニスタ!」を聴き返して、悪くないなと思うようになった。
この方は今も亡くなられた奥さんと一緒にクラッシュを聴いているのかもしれない。でも、そういった心境の変化を、ラジオはぶしつけに解釈するわけではない。ただそこにいるリスナーの間で、共有されます。
その感覚は、精神療法、特にオープン・ダイアローグの理念にとても近いように思います。医師、看護師、患者といった上下関係はなく、3人以上で輪になって対話する。それぞれが対等に「私は~思う」(Iメッセージ)と意見を言い合い、その人がいないところではその人の話をしない。
なんとなくラジオが共有する空間と似ていませんか? 村上春樹のデビュー作「風の歌を聴け」も大きなテーマの一つは、ラジオで痛みを共有することでした。この作品は時折、ラジオDJの語りが挿入される構成になっていますが、終盤で、そのラジオDJに難病の少女からの手紙が届きます。
彼女は「脊椎の病気で寝返りをうつこともできない。手術の成功の可能性も極めて低い。一回でもいい、病院の窓から見える港まで歩いて、海の空気を吸えたら」という内容を書いています。DJは手紙を読んで、夜、港まで歩き、その少女の病院の窓が見えないか、辺りを眺めます。たくさんの灯りがあって、たくさんの人がいる。もちろんラジオのリスナーも含まれる。そう考えて僕は泣いた。君に同情したわけじゃない。泣いた理由は
「僕は・君たちが・好きだ」ということ。
2009年に亡くなった忌野清志郎のラスト・ワンマンのCDが4月に出ました。清志郎は「トランジスタ・ラジオ」など名曲を連発した末に「また会いましょう。愛してます」と締めくくっていました。清志郎のライブは一度しか観たことがなかったけど、大きな会場でも、彼はお客さん1人1人と1対1でした。